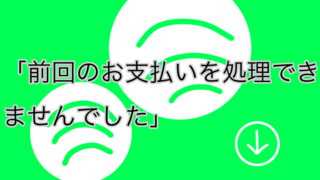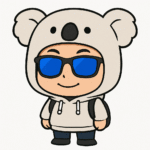ゆーかりってなんだっけ、、、シロコアラです
今回は、大人が無意識にのうちに、子供についてしまっている「嘘」について、考えてみました!
幼少期の「嘘」と子どもの信頼関係 〜3歳児に対して親が守るべき言葉の大切さ〜
子育てをしていると、日々の中でつい口から出てしまう何気ない言葉があります。その一言が、子どもの心にどのような影響を与えているか、改めて考えたことはあるでしょうか。
特に3歳前後の幼少期は、言葉の意味を表面的にではなく、真剣に受け止める時期です。言葉を通じて、世界のルールや人との関わり方を学び始める重要な時期でもあります。だからこそ、「親が嘘をつかない」という姿勢は、子どもの信頼形成において極めて重要な鍵を握っています。
「全部食べないと、お出かけできないよ」——その一言の裏にあるリスク
ある日、3歳の子どもがご飯を残そうとしたとき、「全部食べないとお出かけできないよ」とつい言ってしまった。こうした声かけは、多くの家庭でよくあるしつけの一環かもしれません。
しかし、実際には少しぐらい残してしまっても、その後、親は子どもと予定通りお出かけをする事もあるかと思います。このとき、子どもが受け取るメッセージは、「全部食べなくても、結局行けるんだ」という結果です。そしてさらに深いレベルでは、「親の言っていることは、実際にはそうならないこともある」という認識が芽生えてしまいます。
このような小さな「嘘」は、親にとっては悪気のない方便かもしれません。しかし、子どもはその真意を理解できる年齢ではなく、言葉をそのまま信じて行動します。だからこそ、日常の何気ない一言でも、子どもにとっては“信頼の土台”を揺るがす原因になりうるのです。
「もう知らないよ」は、本当に伝えたい言葉?
育児において、親のイライラが爆発する瞬間もあります。「もう知らないよ!」という一言は、親が限界を迎えたときのサインでもあるでしょう。でも、それを言われた子どもはどう感じるのでしょうか。
3歳児は、親からの愛情を軸に自分の世界を築いています。その親から「知らない」と言われることで、見捨てられたような不安感や混乱を抱えることがあります。そして次に、「でも実際にはお世話してくれるじゃん」という現実を体験すると、またしても「親は言っていることとやっていることが違う」と気づくのです。
こうしたやりとりが重なると、子どもは親の言葉を深く信じなくなっていきます。そしてそのまま成長すると、「本音と建前を使い分けるのが当たり前」「嘘も必要だ」という価値観が、無意識に刷り込まれてしまう可能性があります。
「嘘の境界線」は、大人と子どもではまったく違う
大人同士であれば、場の空気を和らげるためのジョークや方便も理解できます。しかし、子どもはまだ「言葉=真実」という感覚で生きています。
例えば、「おばけが出るよ」「警察に連れて行かれるよ」といった脅し文句も、子どもは本当に怖がります。そして、実際にそんなことは起こらないと気づいたとき、「親の言葉は信じられない」という経験として記憶されてしまうのです。
一度信頼を失ってしまうと、それを取り戻すのには時間とエネルギーが必要です。だからこそ、子どもに対しては、できる限り正直で一貫性のある言葉かけを心がけたいものです。
親が誠実であることが、子どもの信頼の土台を築く
「嘘をつかない子に育てたい」——それは多くの親が願うことでしょう。しかし、それを実現するには、まず親自身が誠実である必要があります。
日々の生活の中で、子どもに対して伝える言葉が、行動と一致しているかどうか。たとえ口から出てしまったことが結果的に実現しなかったとしても、「ごめんね、さっきは〇〇って言ったけど、こういう理由で変わったんだ」と丁寧に伝えれば、それは嘘ではなく「事情の説明」になります。
親が子どもに対して正直であろうとする姿勢は、必ず伝わります。子どもは親の背中を見て育ちます。言葉だけでなく、行動や表情、態度すべてから「信じていい相手かどうか」を学んでいるのです。
信頼関係が育つと、子どもは自然とルールを守るようになる
「全部食べないと出かけられない」といった“条件付きのしつけ”をやめてみると、最初はうまくいかないこともあるかもしれません。でも、信頼関係が育つと、子どもは自然と親の言葉に耳を傾けるようになります。
「今日はお出かけする予定だけど、その前にご飯をできるだけ食べてくれると嬉しいな」と、願いや気持ちを伝える形に変えてみるのも一つの方法です。それを繰り返すことで、子どもは「親の言葉には意味がある」と理解し、行動にも反映されるようになります。
信頼があるからこそ、親の言葉が届き、子どもは「守ろう」と思えるのです。
親も完璧でなくていい。ただ、「正直」であろうとする姿勢が大事
もちろん、子育てにおいて完璧な言葉選びは不可能です。親も人間ですから、感情的になったり、つい適当な言葉を使ってしまうこともあります。
大切なのは、そのあとどう向き合うかです。子どもが混乱していそうなときは、「さっき言ったこと、ちょっと言いすぎちゃったね。本当は〇〇っていう気持ちだったんだよ」と修正することも、誠実さの一部です。
間違いを認める姿勢は、むしろ子どもにとって「人は失敗してもいい」「大切なのはそのあとどうするか」という、人生において重要な学びにつながります。
まとめ:子どもの心に残るのは、親の言葉の「本気度」
子育ては、正解があるようでない世界です。しかし確かなのは、「親が子どもを信じ、正直に向き合うこと」が、信頼の芽を育てるということです。
3歳児のような幼い子どもにとって、親の言葉は絶対的なものです。その言葉が矛盾していたり、実現しなかったりすると、小さな心は混乱し、時には傷つくこともあります。
だからこそ、親の言葉に一貫性を持たせること。そして、時には感情を伝え、時には訂正しながらも、誠実にコミュニケーションを取ること。それが、将来子どもが「信じる力」や「他者との信頼関係」を築いていくための大切な土台になるのです。
「親は嘘をつかない」と子どもが心から感じること。それは、子どもにとって何よりも安心できる心の拠り所です。ぜひ、今日から少しずつ、言葉を選ぶ時間を大切にしてみてください。